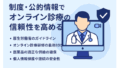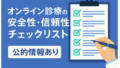医師法・医療法から見たオンライン診療の位置づけ
オンライン診療はスマートフォンやパソコンを使い、自宅にいながら医師の診察を受けられる新しい医療サービスです。しかし、患者にとって気になるのは「法律的に本当に大丈夫なのか?」という点でしょう。日本では、医療に関する基本的なルールは 医師法 と 医療法 という二つの法律に定められています。ここでは、それらの法律の観点からオンライン診療がどのように位置づけられているのかを整理します。
無診察治療の禁止(医師法第20条)
医師法第20条には、「医師は、自ら診察しないで治療をしてはならない」という規定があります。これが、いわゆる 「無診察治療の禁止」 と呼ばれるものです。
この条文だけを読むと、オンライン診療は「診察していないのに薬を出す行為」ではないかと誤解されるかもしれません。しかし厚生労働省は、映像や音声を用いた診察も「診察」に含まれると解釈しています。つまり、ビデオ通話やオンラインシステムを通じて医師が患者の状態を把握していれば、法律上は診察を行ったことになり、無診察治療には該当しないのです。
ただし、電話やチャットのみで診療を行い、患者の状態を十分に把握できないまま薬を処方するようなケースは「無診察治療」と判断される可能性があります。そのため、オンライン診療を行う際には、画像と音声による対面性を担保する仕組み が必要とされているのです。
医療法における診療体制の位置づけ
次に医療法について見てみましょう。医療法は、医療機関の設置や管理に関するルールを定めた法律であり、オンライン診療そのものを直接規定している条文はありません。しかし、医療法に基づく「医療提供体制」の中に、オンライン診療は組み込まれる形で運用されています。
厚労省が示す「オンライン診療の適切な実施に関する指針」では、オンライン診療はあくまで 「対面診療を補完する手段」 であるとされています。つまり、対面診療の代替ではなく、患者の利便性を高めるための補助的な位置づけです。特に初診は原則として対面で行う必要があり、再診においても定期的な対面診療が求められる点が重要です。
新型コロナウイルス感染症による特例
2020年、新型コロナウイルス感染症の流行をきっかけに、オンライン診療の規制は一時的に大幅に緩和されました。従来は「初診は原則対面」が大前提でしたが、感染拡大防止の観点から 初診からオンライン診療が可能 となったのです。
ただし、これは時限的・特例的な措置であり、将来的には再び規制が強化される可能性もあります。そのため、オンライン診療を利用する患者としては、「法律や指針の改正動向」を常にチェックしておくことが大切です。
オンライン診療の法的リスクと安全性
法律的にはオンライン診療は認められていますが、リスクがゼロではありません。たとえば、
-
画面越しでは診断精度が下がる可能性がある
-
薬の処方に関して十分な説明が得られない場合がある
-
通信環境の不備で診察が中断される
といった課題が残っています。
しかし、厚労省の指針に従い、定期的な対面診療を組み合わせて実施しているクリニックであれば、法律的にも安全性が担保されやすいといえるでしょう。患者としては、安易に「完全オンライン完結」とうたうサービスだけで判断せず、法的ルールに準拠したクリニックかどうか を見極めることが重要です。
まとめ
オンライン診療は医師法第20条に違反する「無診察治療」には当たらず、医療法に基づく医療提供体制の一部として認められています。ただし、厚労省の指針では「初診は原則対面」「再診も定期的に対面を組み合わせる」といった条件が課されています。
つまり、法律的には許されているものの、条件付きで運用されているのが実態です。オンライン診療を安心して利用するためには、こうした法律の位置づけを理解し、ルールに準拠したクリニックを選ぶことが不可欠といえるでしょう。
✅ 参考文献
-
厚生労働省「オンライン診療の適切な実施に関する指針」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/online_shinryou/index.html -
e-Gov法令検索「医師法」
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=323AC0000000201 -
e-Gov法令検索「医療法」
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=323AC0000000205
厚労省の統計で見るオンライン診療の普及率と利用動向
オンライン診療は、2018年の制度化以降、少しずつ医療現場に浸透してきました。しかし、本格的に普及が進んだのは新型コロナウイルス感染症の流行以降です。感染拡大防止の観点から、厚生労働省は規制を大幅に緩和し、初診からでもオンライン診療を可能とする特例措置を導入しました。この背景を踏まえて、厚労省や総務省が発表している統計データをもとに、オンライン診療の現状と今後の動向を整理します。
オンライン診療導入医療機関の推移
厚労省の発表によれば、2020年4月時点でオンライン診療を導入していた医療機関は全国で約1万施設程度でした。しかし、新型コロナの流行と特例措置により、2021年には約1.6万施設に拡大しました。
2023年度のデータでは、オンライン診療に対応している医療機関は 全国の約20% に達しています。特に都市部では診療所・クリニックを中心に導入が進んでおり、患者の利便性を高める取り組みが広がっています。
👉 厚労省「オンライン診療の取組状況」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00001.html
診療科別の導入状況
診療科ごとに見ると、オンライン診療の導入率には大きな差があります。
-
精神科・心療内科 … 定期的な投薬やカウンセリングが中心のため導入が進んでいる
-
皮膚科 … 患者が画像を送信できるため比較的診断が容易で導入しやすい
-
内科(生活習慣病) … 高血圧や糖尿病など慢性疾患の再診に有効
-
小児科・耳鼻科 … 子どもの急性疾患や耳鼻の症状はオンラインだけでは診断が難しく、導入は限定的
このように、オンライン診療は「慢性疾患や経過観察が中心の診療科」で特に普及していることがわかります。
患者利用率の実態
厚労省が公表した「オンライン診療の実態調査」(2022年度)によると、過去1年間にオンライン診療を利用したことがある患者は全体の約7% にとどまっています。
その内訳を見ると、
-
利用経験者の多くは30〜40代の都市部在住者
-
利用目的は「再診・薬の処方」が中心
-
初診で利用したケースはまだ少数
という傾向が見られました。利用率がまだ低い理由としては、
-
「対面診療に比べて安心感が少ない」
-
「対応しているクリニックが限られている」
-
「制度や料金がわかりにくい」
といった点が挙げられています。
普及を後押しする要因
オンライン診療の普及には、いくつかの社会的要因が影響しています。
-
高齢化と慢性疾患の増加
定期的な受診が必要な患者が増えており、移動負担を軽減できるオンライン診療は需要が高い。 -
ICTインフラの整備
5Gや光回線の普及により、映像品質が向上し、診療精度が高まりつつある。 -
規制緩和の継続
特例で認められた「初診からのオンライン診療」について、厚労省は恒久化を検討中。 -
製薬会社・配薬システムとの連携
薬局と連携した配送体制が整い、薬の受け取りもスムーズになってきた。
今後の展望
厚労省は今後の医療提供体制において、オンライン診療を「対面診療の代替」ではなく「補完的手段」として位置づけています。しかし、制度の恒久化や診療報酬の改定によって、さらに普及が進むと見られています。
特に注目されているのは、
-
高血圧・糖尿病など生活習慣病患者への定期診療
-
在宅医療との連携(訪問診療と組み合わせ)
-
地域医療格差の是正(過疎地・離島での活用)
これらの分野でオンライン診療の利用が広がることで、患者の負担軽減や医療資源の効率化につながる可能性が高いでしょう。
まとめ
厚労省の統計からは、オンライン診療がここ数年で急速に普及してきたことが読み取れます。ただし、まだ利用経験者は一部にとどまり、課題も残っています。今後は規制緩和やICTインフラの発展によって利用率がさらに拡大し、日常的な診療の一部として定着していくと考えられます。
✅ 参考文献
-
厚生労働省「オンライン診療の取組状況」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00001.html -
厚生労働省「オンライン診療の適切な実施に関する指針」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/online_shinryou/index.html -
総務省「情報通信白書」
https://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/
個人情報保護法とオンライン診療|プライバシーはどう守られる?
オンライン診療は便利で身近な医療の形として普及が進んでいますが、その一方で「自分の診療情報や健康データは本当に安全なのか?」という不安を持つ人も少なくありません。診察内容や処方情報は、極めてセンシティブな個人情報です。もし流出したり、第三者に不正利用されたりすれば、患者の生活に大きな影響を及ぼします。こうしたリスクを防ぐため、日本では 個人情報保護法 をはじめとする法律が整備されており、オンライン診療サービスもそのルールに従って運営されています。
ここでは、オンライン診療における個人情報保護の仕組みについて解説します。
個人情報保護法における医療情報の位置づけ
日本の「個人情報の保護に関する法律(個人情報保護法)」では、医療情報は「要配慮個人情報」に分類されます。要配慮個人情報とは、人種、信条、病歴、犯罪歴など、取り扱いに特別な配慮が求められる情報のことです。
診療記録、処方履歴、検査結果などは、まさにこの「要配慮個人情報」に該当します。事業者は本人の同意なく収集・利用することができず、厳格な管理体制が求められています。
オンライン診療システムに求められるセキュリティ基準
厚労省の「オンライン診療の適切な実施に関する指針」では、オンライン診療を行う際に使用するシステムについても基準が定められています。
-
通信の暗号化(TLS/SSLの導入)
-
利用者認証(ID・パスワード管理、多要素認証)
-
ログ管理(アクセス履歴を保存し、不正利用を検出可能にする)
-
データ保存の安全性(国内サーバーの利用や厳格なアクセス制御)
これらの要件を満たすことで、患者と医師の間で交わされる診療情報が第三者に漏洩するリスクを大幅に下げることができます。
個人情報保護委員会の役割
オンライン診療におけるプライバシー保護を監督しているのが 個人情報保護委員会 です。事業者が個人情報保護法に違反している場合、委員会は勧告・命令を出すことができ、最悪の場合は業務停止を命じることも可能です。
実際に過去には、患者情報を不適切に扱った事例に対して行政処分が行われたケースもあります。こうした監督体制があることで、患者は安心してオンライン診療サービスを利用できるようになっています。
患者自身ができるプライバシー対策
法律や制度だけでなく、患者自身ができる対策も重要です。たとえば、
-
診療アプリの提供元を確認する(厚労省の指針に準拠しているか)
-
ログイン情報を適切に管理する(使い回しパスワードを避ける)
-
通信環境に注意する(公共Wi-Fiでは利用しない)
-
怪しい広告や非公式アプリを避ける
これらを徹底するだけでも、プライバシーリスクは大幅に減らすことができます。
海外との比較
アメリカや欧州では、医療情報の保護に関してより厳格なルールが定められています。
-
米国:HIPAA(医療保険の相互運用性と説明責任に関する法律) が医療データの保護を規定
-
EU:GDPR(一般データ保護規則) により、医療データの扱いは最も厳格なカテゴリーに分類
日本の個人情報保護法も国際基準に沿って改正が進められており、2022年の改正では罰則強化や越境データ移転への規制が追加されました。今後、日本でも欧米並みに厳しい基準が求められていくと考えられます。
まとめ
オンライン診療は利便性が高い反面、個人情報漏洩というリスクを抱えています。しかし、個人情報保護法をはじめとする法的枠組み、厚労省の指針、そして個人情報保護委員会の監督によって、安全性は一定程度担保されています。
患者としては、法律や制度を理解することに加え、自分自身でアプリの選び方や利用環境に気をつけることが大切です。プライバシーが守られてこそ、安心してオンライン診療を活用できるといえるでしょう。
✅ 参考文献
-
e-Gov法令検索「個人情報の保護に関する法律」
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=415AC0000000057 -
厚生労働省「オンライン診療の適切な実施に関する指針」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/online_shinryou/index.html -
個人情報保護委員会「個人情報保護法について」
https://www.ppc.go.jp/personal/
地方自治体や国の補助制度|オンライン診療支援の事例
オンライン診療は都市部だけでなく、医療資源が不足する地方や過疎地でも注目を集めています。医師不足や交通の不便さといった課題を解消するために、国や地方自治体が補助制度やモデル事業を展開してきました。ここでは、オンライン診療を支える行政の取り組みや、具体的な支援事例を整理します。
国の取り組み:遠隔医療モデル事業
厚生労働省は、2016年度から「遠隔医療モデル事業」を推進してきました。この事業は、特に医師不足が深刻なへき地や島しょ部を対象に、ICTを活用して都市部の専門医と地域医療機関を結びつけるものです。
モデル事業の中では、
-
慢性疾患患者の遠隔診療
-
専門医による画像診断の共有
-
在宅医療と連携したモニタリング
といったケースが試行され、効果が検証されてきました。この成果を受けて、2020年以降はコロナ禍を背景に全国規模でオンライン診療の制度化が加速しています。
👉 厚労省「遠隔医療モデル事業」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411.html
自治体による補助金制度の事例
地方自治体でも、オンライン診療を導入する医療機関や患者に対して補助制度を設けるケースが増えています。
-
北海道
道庁が医療過疎地域における遠隔診療の導入を支援。診療所への機器導入費用を一部補助。 -
長野県
山間部や豪雪地帯の住民を対象に、オンライン診療を利用した場合の費用を補助。 -
沖縄県
離島地域でのオンライン診療を推進。島内の診療所と本島の専門医を結び、診断精度を向上。
これらの取り組みは、単なる「診療の効率化」ではなく、地域住民の命を守る医療インフラとしての役割を担っています。
学校や介護施設でのオンライン診療活用
補助制度は医療機関だけでなく、教育・福祉の現場でも活用されています。
-
学校保健との連携
一部の自治体では、学校に通う子どもの健康相談にオンライン診療を導入。専門医が遠隔で対応し、早期発見・早期治療につなげている。 -
介護施設での導入
高齢者施設では、夜間や休日の緊急時にオンライン診療を利用する事例が増加。医師の往診が難しい地域でも、迅速な判断が可能になっている。
こうした導入は、医療と教育・福祉を結びつける新しい形として注目されています。
総務省のICT補助とオンライン診療
総務省も、医療分野でのICT活用を後押ししています。「地域医療情報連携ネットワーク整備事業」では、オンライン診療に必要な通信インフラやセキュリティ環境の整備に助成を行いました。
これにより、過疎地や島しょ部でも安定した通信環境が整備され、オンライン診療の品質が向上しています。
👉 総務省「ICT地域活性化事例」
https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/ictseisaku/
今後の課題と展望
補助制度やモデル事業によってオンライン診療は広がりを見せていますが、課題も残されています。
-
医師と患者双方のICTリテラシー不足
-
高齢者世帯における機器操作の難しさ
-
継続的な補助金確保の必要性
こうした課題を乗り越えるためには、単発の補助ではなく 「恒常的な制度化」 が求められます。厚労省も2024年度以降、診療報酬改定の中でオンライン診療の評価を見直し、より利用しやすい仕組みを検討中です。
今後は、自治体ごとの取り組みが全国的に共有され、地域格差を埋める方向で制度が整備されていくと考えられます。
まとめ
オンライン診療は、国の遠隔医療モデル事業や地方自治体の補助制度によって支えられてきました。特にへき地や離島では、補助金や実証事業が患者の命を守るライフラインとして機能しています。
今後はこれらの制度を恒久的に整備し、誰もが安心してオンライン診療を利用できる環境を整えることが求められています。
✅ 参考文献
-
厚生労働省「遠隔医療モデル事業」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411.html -
厚生労働省「オンライン診療の適切な実施に関する指針」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/online_shinryou/index.html -
総務省「ICT地域活性化事例」
https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/ictseisaku/
患者が確認できる公的情報源まとめ|信頼できるサイト一覧
オンライン診療を安心して利用するには、信頼できる情報源にアクセスできるかどうかが大きなカギとなります。インターネット上には個人の体験談や匿名掲示板の書き込みなど、必ずしも正確でない情報も数多く存在します。そのため、厚労省や国の専門機関が発信する一次情報を確認することが重要です。ここでは、患者が実際に役立てることができる公的情報源を一覧にまとめ、それぞれの特徴や活用方法を解説します。
厚生労働省(オンライン診療・医療制度全般)
厚生労働省は、日本の医療制度を管轄する行政機関であり、オンライン診療に関する指針や制度改正の情報を随時公開しています。
-
オンライン診療の適切な実施に関する指針
医師がオンライン診療を行う際に遵守すべきルールをまとめた文書。初診や再診の条件、医師研修の有無、診療報酬上の扱いなどが解説されています。 -
遠隔医療に関するQ&A
患者向けに「どのような診療科で利用できるのか」「費用はどうなるのか」などをわかりやすく整理。
👉 厚生労働省「オンライン診療の適切な実施に関する指針」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/online_shinryou/index.html
PMDA(医薬品医療機器総合機構)
PMDAは医薬品や医療機器の安全性を監督する独立行政法人です。オンライン診療を通じて処方される薬も、すべてPMDAの承認制度を通過したものでなければなりません。
-
医薬品の添付文書データベース
薬の用法・用量、副作用、禁忌事項が確認できる一次情報。患者が処方薬の正しい情報を入手するのに必須。 -
副作用被害救済制度
適正に使用したにもかかわらず重い副作用が出た場合に救済が受けられる制度。給付内容や申請方法もサイトで解説。
👉 PMDA「医薬品医療機器情報提供」
https://www.pmda.go.jp/
国民生活センター(トラブル相談・消費者保護)
国民生活センターは、消費者トラブル全般に関する相談窓口を提供しています。オンライン診療に関連しても、解約トラブルや高額請求などの相談が寄せられています。
-
PIO-NET事例検索
過去に報告された消費者トラブルの事例を確認できる。オンライン診療関連では「薬が届かない」「キャンセル料トラブル」などの事例が掲載。 -
消費者ホットライン(188)
電話一本で地域の消費生活センターにつながり、相談できる体制が整っている。
👉 国民生活センター
https://www.kokusen.go.jp/
国税庁(医療費控除の情報)
オンライン診療でかかった費用は、条件を満たせば医療費控除の対象になる場合があります。国税庁の公式サイトでは、その取り扱いや申請方法を確認できます。
-
タックスアンサー(よくある質問)
医療費控除に該当するケース、対象外となる自由診療の扱いなどをQ&A形式で解説。
👉 国税庁「医療費控除」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1120.htm
個人情報保護委員会(プライバシー保護)
オンライン診療では、診療記録や処方履歴といった要配慮個人情報が扱われます。そのため、個人情報保護法に基づき、事業者は厳格に管理する義務があります。
-
ガイドライン・Q&A
医療分野における個人情報の取り扱いを整理した資料を公開。患者自身が「どこまで同意が必要か」を理解するのに役立つ。
👉 個人情報保護委員会
https://www.ppc.go.jp/
情報源の使い分け方
これらの公的情報は、それぞれ役割が異なります。
-
制度やルールを調べたいとき → 厚労省
-
処方薬の情報や副作用救済 → PMDA
-
契約や料金トラブル → 国民生活センター
-
医療費控除など税務関連 → 国税庁
-
プライバシーの扱い → 個人情報保護委員会
患者はこれらを知っておくことで、万が一トラブルや疑問があった場合に、信頼できるルートから解決策を得られるようになります。
まとめ
オンライン診療を利用する上で、患者が最も頼るべきは公的機関の情報です。厚労省、PMDA、国民生活センター、国税庁、個人情報保護委員会といった一次情報源を活用することで、誤情報に惑わされず、安全にサービスを利用できます。
特に匿名の口コミや体験談は、参考になる一方で誤解を生む可能性もあるため、公的情報と併せてバランスよく判断することが大切です。
✅ 参考文献
-
厚生労働省「オンライン診療の適切な実施に関する指針」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/online_shinryou/index.html -
PMDA「医薬品医療機器情報提供」
https://www.pmda.go.jp/ -
国民生活センター
https://www.kokusen.go.jp/ -
国税庁「医療費控除」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1120.htm -
個人情報保護委員会
https://www.ppc.go.jp/